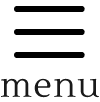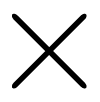お知らせ・コラム
- 2026-01(2)
- 2025-12(2)
- 2025-11(5)
- 2024-12(1)
- 2024-09(1)
- 2024-01(1)
- 2023-11(1)
- 2023-06(1)
- 2023-04(1)
- 2023-03(1)
- 2023-01(1)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-10(1)
- 2022-09(2)
- 2022-07(1)
- 2022-05(2)
- 2022-03(1)
- 2022-02(1)
- 2022-01(1)
- 2021-12(2)
- 2021-11(1)
- 2021-10(1)
- 2021-09(1)
- 2021-07(2)
2025/11/13
Sarry’s Notes #3.芸術の秋、国宝

「国宝?ワタシはいつでもお母さんの宝だけど?✨」
2025年を振り返る季節となりました。
今年の映画で話題作といえば、やはり「国宝」でしょうか🎞🎬
️
6月の公開からなおロングヒットを続け興行収入も邦画実写の歴代最高記録を塗り替える勢いです。
私もこの映画は大画面でしっかりと映像美も含め堪能いたしました。
日本の伝統芸能でありながら現在はどこか特殊な娯楽に位置付けられている、
歌舞伎と世襲(血縁)が映画の核となっています。
歌舞伎役者ではない俳優さんが、見事に「歌舞伎役者」演じていることに感動しました🥹
私は若い頃に歌舞伎の世界で仕事をしていたことがあるのですが、舞台で演じられる歌舞伎が面白くて魅了されていたかというと、、、そうでもありませんでした笑😅
それより舞台に向かう役者の方々の姿勢や残っている風習、お芝居の中に隠れている美学などがとても好きでした。
楽屋口には神棚があり毎日手を合わせてから舞台に臨む。
楽屋の暖簾一枚で役者部屋と控え部屋が分かれていますが、その暖簾一枚を境に、スポットライトを浴びる“舞台”への敬意が芽生え、自然と振る舞いにも表れていたと思います。
また夏の暑さが増してくるとスーツ姿で働くスタッフだって汗だくです💦
そんな時に楽屋に「暑中につき無礼講」という貼り紙が出されるのです📝
楽屋内での行動や身だしなみが多少崩れても良しとしますよ、という意味です。
するとスタッフもスーツのジャケットを脱いだり、役者は部屋着から浴衣で歩くことが許されるのです👘
暑がりのわたしは貼り紙が出るのをよく待っていたなぁ☀️
名優と言われた歌舞伎役者の女形さんは、心中する物語を演じる際は舞台袖で氷水で手を冷たくして舞台に出ていくと聞いたことがあります。
共演する立役(男役)に自分の冷たい手に触れた際に、心中する覚悟の想いをより強く感じて頂けるからという工夫です。
またある芝居の中で「雪道を下駄で歩く」というシーンがあり、実際に雪の日に下駄で歩く練習に付き合ったことがあります☃️
雪の感触からの下駄の足捌きや体感を味わいたかったのでしょう。
*二代目市川團十郎
早口言葉で有名な「外郎売」という歌舞伎の演目があります。
現在でもアナウンサーの滑舌の練習に使われていますが、歌舞伎十八番と呼ばれる演目の一つです。
この演目は今から300年ほど前に二代目市川團十郎によって初演されました。
初代の市川團十郎という人は当時のスーパースター&アイドルのような人だったそうです💡今で言うキムタク?!(ちょっと古いかもしれませんがまさに国民的スター)
初代市川團十郎の着ている服や髪型をみんなが真似するという、まさにブームの火付け役!二代目團十郎はその息子ですが、初代が亡くなってから二代目を襲名し得意とした演目が外郎売でした。
その二代目市川團十郎の外郎売で面白いエピソードが残っています。
ある時、外郎売で颯爽と花道に登場した二代目團十郎に、酒に酔った観客の一人が見どころの早口言葉を先に全て客席から言ってみせた😳
一瞬静まり返った場内に向かって、二代目團十郎はゆっくりと落ち着いて一言
「半畳賜りありがとうございます」
と言って、逆さまから全ての早口言葉を誦じてみせ、観客は舌を巻き拍手喝采となった👏というものです。
役者の演技に対して観客が不満を表す際に、畳を投げ入れる仕草から「半畳を入れる」という言葉が生まれました。
二代目團十郎は観客の野次にお礼のパンチを入れてから、ギャフンと言わせる切り返しをしたというワケです🤛
これはわたしの大好きなエピソードなのですが、聞いた時は
なんてカッコイイんだろう!これぞ江戸っ子!粋だなぁ〜”と痺れてしまいました😍
映画、美術、芸術🎨
過ごしやすい季節の今はお出かけにもピッタリですね🍂
お出かけの際のペットのお留守番はしっかりサポートさせていただきます🐾
ご相談やお問い合わせはお気軽にどうぞ😊